今日はGoizueta Business Schoolでのロジカルシンキング・課題解決の学びについて記載しようと思います。GoizuetaのMBAでは最初の秋学期にIMPACTという授業の中で徹底的に学びます。ロジカルシンキングといえば、新入社員研修でも似たようなフレームワークを学ぶ企業は多いかもしれません。MECEやらロジックツリーといった言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。これが、ビジネス課題に取り組む上で非常に重要なスキルであり、今後のキャリアにも大いに役立つと感じました。
クリティカルシンキングとは?
そもそもクリティカルシンキングとは何なのか?それは問題を深く掘り下げ、論理的に分析し、最適な解決策を見つけ出すための思考法です。どんなビジネスにおいても、問題解決の力は必要不可欠です。IMPACTの授業では、理論的な学びを実務にどう活かすかが重要で、課題解決のフレームワークを体系的に学ぶことが求められます。
クエスチョンツリーとアンサーツリー
IMPACTの授業では、クリティカルシンキングの基礎を築くために、様々なフレームワークを使って、問題解決のプロセスを深く学びました。これらがどのように機能するのかを簡単に説明します。
クエスチョンツリー(Question Tree)
- まずクエスチョンツリーは、問題を細分化していくための手法です。大きな課題をいくつかの小さな質問に分解し、その質問に答えることで、解決すべき問題が明確になり、より実行可能なステップに落とし込むことができます。
- 例えば、「売上が減少している」という問題があった場合、それを「顧客数が減少したのか?」「単価が下がったのか?」といった具体的な質問に分けていきます。これにより、根本的な原因が明確になります。
アンサーツリー(Answer Tree)
- 次に、クエスチョンツリーで分解した質問に対する答えを集めるのがアンサーツリーです。この段階では、仮説を立て、データを収集し、論理的に答えを導き出します。
- アンサーツリーでは、具体的な解決策を考えるために、「もしこの答えが正しいなら、どのようなアクションを取るべきか?」という視点で進めていきます。最終的に、問題に対する最適な解決策を見つけるために、答えを組み合わせていくことが求められます。
ミーシー(MECE)
続いてMECEは、Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive(相互に重複せず、全体として漏れがない)の略で、問題を整理する際の基本原則です。簡単に言うと、「ダブりなく、モレなく」情報を分類することです。
クエスチョンツリーを作るときにMECEを意識することで、問題を体系的に整理できます。また、アンサーツリーでは、MECEを意識して「仮説」を整理し、優先順位をつけて検証することが重要です。つまりクエスチョンツリーからアンサーツリーの作成には、MECEという視点が欠かせません。
次章から実際にIMPACTの授業で扱ったケーススタディをご紹介しようと思います。
Case:精密農業を展開するための最適な国選定
米国内で成功を収めたあるユニコーンアグリテック企業が国際市場へ展開する機会を検討している。ブラジル、フランス、インド、ドイツ、メキシコのうちどの国をターゲットとすべきか?
扱っている製品の性能や適用モデルの情報等、膨大な背景情報がありますが、ここではケースのポイントを簡潔にまとめました。この課題について2カ月ほど費やし、アウトプットまで持っていきました。以下に私たちがブラジルを選定したアプローチを簡単に記載します。(プレゼンテーション時間20分という制約があったため、そぎ落とした情報も多々あります)
NPV最大化を軸とした市場選定のアプローチ
私たちは、市場投入7年後の純利益を最大化する国を見極めるため、以下の要素を分析しました。
市場規模と普及率の評価
まずは各国の精密農業の市場規模、普及率、予想単価を総合的に比較し、トップライン売上が最も高くなる市場を特定しました。
- ブラジルは世界有数の農業大国であり、農地面積が広大であることから、精密農業技術の導入による生産性向上の余地が大きいと判断しました。
- 既存の精密農業技術の普及率はまだ低く、成長のポテンシャルが高い点も魅力的でした。
コスト面での優位性
続いて収益面での差別化優位を確立するため、最低賃金や土地の賃借料を比較しました。
- ブラジルの労働コストと土地コストは他の候補国に比べて低く、コスト競争力を持てる可能性が高いと分析しました。
- インフラ整備は課題ではあるものの、政府の農業支援策が充実しており、技術導入を後押しする環境が整いつつある点も評価しました。
市場の成熟度と戦略的決定
その後、各国の精密農業市場の成熟度を分析し、市場投入後の成長曲線を想定しました。
- フランスやドイツなどの欧州市場はすでに精密農業が一定の成熟度に達しており、新規参入のハードルが高い可能性があると判断しました。
- 一方で、ブラジルは農業分野でのデジタル化が進行中であり、市場参入によるNPVの増加余地が大きいと結論づけました。
ターゲット市場と製品開発の方向性
次に、どのような製品を開発すべきか?という視点で分析を行いました。
農家のアンメット・ニーズを特定
- 労働力不足:ブラジルでは農村部の労働力が減少しており、農業の自動化・効率化ニーズが高い。
- 農家の教育不足:精密農業の導入には、技術リテラシー向上のための教育支援が不可欠。
製品提供モデルの評価
提供モデルとして、以下の3つの方式を検討しました。
- フルサービス運用(FSO):企業がすべての機器を提供・運用するモデル。
- 機器販売(EaaP):農家が自ら機器を購入・管理するモデル。
- 機器のサブスクリプション(EaaS):農家が機器をレンタルするモデル。
- ブラジルでは資本力のある大規模農家がターゲットとなるため、EaaP(機器販売)モデルを中心に展開するのが最も有望と考えました。
- 一方で、中規模農家や新規参入農家向けには、導入しやすいEaaS(サブスクリプション)も併用することで、市場の広がりを狙う戦略を立案しました。
供給・流通・国際オペレーションの設計
その後、どのように供給・流通を設計し、現地での事業運営を確立するかを検討しました。
流通経路の分析
- 地元の独立系ベンダーが市場を支配しているか?
- 農家の購買行動(直接購入か?販売代理店を通すか?)
- 農業機器の契約形態(リース vs 購入)
ブラジルでは、農業機器の販売チャネルとして既存のディストリビューターが強い影響力を持っていることがわかりました。したがって、現地の流通網と提携することが成功のカギになると判断しました。
国際オペレーションの確立
- オフショア・オフィスの設置:現地でのカスタマーサポートを強化するための拠点を設置する必要があるか検討。
- 現地マネージャーの雇用機会:市場開拓をリードできる人材を確保するための採用戦略を策定。
- 各国へのサポート体制の整備:遠隔サポートやメンテナンスサービスの導入を計画。
このように、ビジネスの成功には単なる市場規模だけでなく、経済性・技術適用性・流通網の整備・政府支援策といった多面的な要素を考慮することが不可欠です。
IMPACTを通じて、データを活用しながら市場を分析し、最適な戦略を立案するスキルを大きく磨くことができました。
実践的な思考力とビジネススキル
Goizueta Business SchoolのIMPACTは、単なるアカデミックな学びにとどまらず、リアルなビジネス課題に挑むことで、実践的なスキルを鍛える場でした。
2か月にわたり、課題に対して仮説を立て、MECEの視点を活用しながらクエスチョンツリーを構築し、最適な戦略を導き出すプロセスを徹底的に学びました。特に、「答えのない問い」に対して、ロジックとデータを武器に意思決定を行うスキルは、今後のキャリアにおいても大きな財産になると確信しています。
また、限られた時間の中で結論を出すプレッシャー、チームメンバーとの意見のすり合わせ、プレゼンテーションの説得力を高める工夫など、実際のビジネス環境に直結する経験ができたことも、IMPACTの大きな価値でした。
「論理的に考える力」「課題を分解し、優先順位をつける力」「チームで動きながら、短期間で高いアウトプットを出す力」。これらを磨きたい人には、間違いなく価値のあるプログラムだと感じました。
IMPACTに興味がある方へ
Goizueta Business SchoolのIMPACTに興味が出た方はこちらの公式サイトを参考にしてみてください。
またIMPACTで学ぶようなロジカルシンキングは「イシューから始めよ」(安宅和人著)で体系的に解説されています。この本についても以前の記事で記載しているので是非ご覧ください。
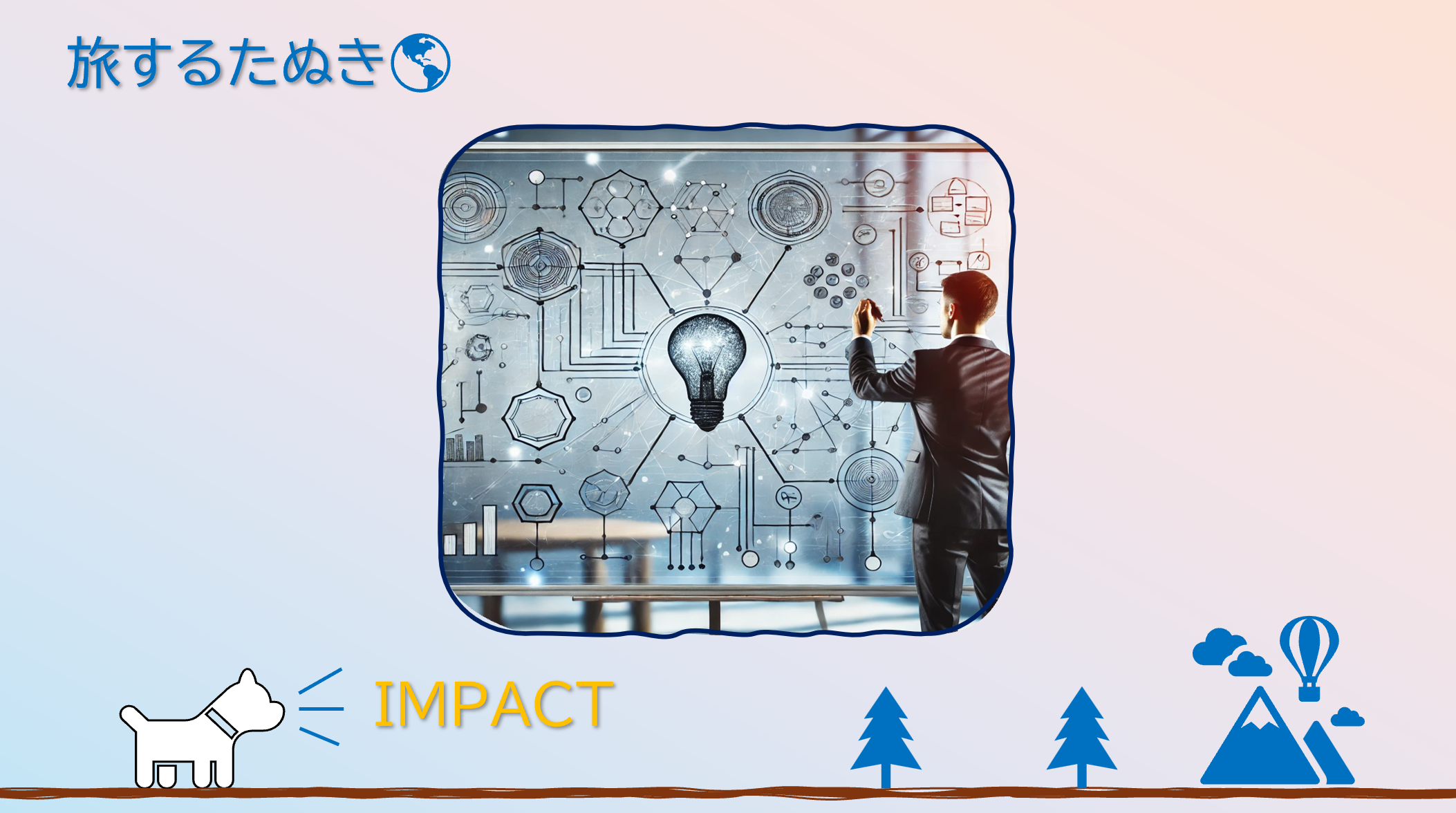
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45591030.518f29fd.45591031.5c60fda2/?me_id=1213310&item_id=21341113&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3563%2F9784862763563_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント